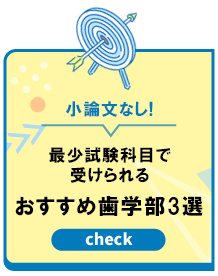国立歯学部と私立歯学部の大きな違いとは
歯学部は全国に29あり、国立が11、公立が1、私立が17です(2022年5月調査時点)。歯科医師になるために学ぶ大学という目的は同じで、6年間通います。歯学部の教育は、「歯学教育モデル・コア・カリキュラム」という教育内容と卒業までの到達目標が示されたガイドラインが制定されているので、ほぼ同じ内容です。
6割がカリキュラムに沿ったもので、残り4割が各大学の独自編成のカリキュラムになります。国立と私立の歯学部にはどんな違いがあるのか見てみましょう。
大きな違いは学費
国立と私立の歯学部で大きく異なるのは学費です。国立歯学部の学費は全国一律で、文部科学省による標準額を基にした入学金や授業料が設定されています。入学金と授業料を併せて初年度は817,800円、6年間合計で3,496,800円必要です。歯学を学ぶには設備を新しいのものに揃えておく必要がありますが、国立の歯学部はそのための費用は国からの援助によって不足分を補い運営しています。
※参照元:メディカルアーク https://www.medical-ark.co.jp/shigaku-jukeninfo/2021dental-tuition/
私立歯学部の学費は大学で施設維持したり設備を新しくしたり、高度な研究など行うための経費を賄う必要があるので入学費や授業料が高くなり、金額は大学によって異なります。6年間の学費で低額と言われる大学は1,918万円、高額な大学では3,354万円にもなり、トータルで1,000万円以上の差があるのです。
学費の高い私立歯学部には奨学金や特待生など学費を軽減できる制度が設けられています。国の教育ローンを利用するというのもひとつの手です。教育ローンと特待生制度を利用することで、入学金など一括で多額の資金が必要な場合も対応でき、学費の高い歯学部を志望することも現実的に考えることができます。
※参照元:メディカルアーク https://www.medical-ark.co.jp/shigaku-jukeninfo/2021dental-tuition/
偏差値が違う
学費以外に、国立と私立歯学部で大きく違うのは偏差値の違いです。学費が安い国立歯学部は学生が集まるため、偏差値は高い傾向にあり、11の国立すべてが60以上の偏差値です。
私立歯学部は偏差値60以上の大学もありますが、多くは40後半から50後半の偏差値になっています。偏差値は大学それぞれですが、国立が高く私立が低いという傾向は否めません。私立歯学部は学費が高いので、学費が低い大学の倍率が上がることがあります。とはいえ受験生は学費だけで志望校を決めているだけではないので、国家試験合格率の高さなども影響しています。
※参照元:マナビジョン https://manabi.benesse.ne.jp/ap/daigaku/search/nanido/
まとめ
国立と私立の歯学部の大きな違いは学費ということがわかりました。6年間トータルの学費が圧倒的に安い国立歯学部を目指す学生が多いのは理解できるでしょう。学費の高い私立歯学部でも奨学金や特待生、教育ローンなどを活用すれば、大きな負担を減らして通うことができます。とはいえ学費が高いことに変わりはありません。
何にお金が必要なのか、国家試験合格率や教育体制が整っているのかなどを確認し、高い学費を無駄にしない大学を選ぶようにしましょう。